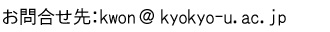研究室紹介
權 眞煥(生活工学・准教授)
自己紹介・メッセージ
生活工学研究室では、人間生活と密接にかかわっている様々な現象を科学的に解明し、家庭や社会生活に有用なテクノロジーをデザインしています。関連学問としては情報学、実験心理学、認知科学、コミュニケーション科学および工学、教育工学などが挙げられます。安全で安心、便利、快適な家庭・社会環境を構築するために必要とされるテクノロジーの提案および教育実践に関する研究を進めています。
また、学校教育におけるAIとICTの活用法および新たな教育環境のデザインについて研究しています。GIGAスクール構想の実現に向け、教育現場では情報機器の導入と通信環境の整備が進んでおり、ICT教育の重要性が増してきています。本研究室ではAIとICTの基礎から授業実践、動画教材の制作・編集技術、ウェブサイトを用いたオンライン学級づくり、AIプログラミング教育をテーマとして進めています。

現在の研究テーマ
1.自閉症スペクトラム障害(ASD)の診断支援システムの開発
自閉症スペクトラム障害(ASD)とは相互的な社会関係とコミュニケーション能力における質的障害を表します。このASD者は世界的に増加傾向にあり、新たな社会現象となっています。しかし、まだASD者に対するバイオマーカー(診断と評価のための指標)は開発されていないのが現状です。本研究ではコミュニケーションにおけるASD者の身体同調特性を解明し、自閉症スペクトラム障害に対する客観的なバイオマーカーを開発することを目的としています。具体的には、位相差検出・分析アルゴリズムを用い、コミュニケーション中に発生したASD者の身体同調特性を科学的に定量化し、健常者との相違、重症度との関連性を検証しています。この成果はASDの早期診断と支援、療育に活用することができます。
2.コミュニケーション状態の可視化
近年は人と人同士だけでなく、人と人工物(ロボットなど)がコミュニケーションを行う時代になりました。本研究では、人の非言語情報を中心にコミュニケーションの特徴を定量的に分析・解明しています。解明された情報を基に、人と人および人と人工物がスムーズにインタラクションできるよう、コミュニケーションサポートシステムを考案・実現することをめざしています。
3.AI・ICT教育の環境デザイン
小・中・高等学校でもICTおよびIoTの導入により、学校教育における情報化が推進されています。本研究では、子供の学習状態の可視化、教師と生徒のコミュニケーションサポート、AI・ICTの導入に関する調査および実践的研究を行っています。また、授業や学習を支援することを目的とした映像コンテンツの制作・編集技術のパッケージ化やウェブサイトを活用したオンライン学級づくりの方法、AIプログラミング教育のための教材の提案を行っています。また、シミュレーション型教材を開発することにより、プログラミングと他教科の横断的な学習の実現をめざしています。
現在の研究テーマ
※著書・論文や学会発表の一覧については、京都教育大学の研究者総覧をご覧ください。
主な担当授業
学 部
生活科学、家庭電気・機械、生活情報処理、学校教育と生活工学、衣生活概論(共担)、小学校教科内容論生活(b)(共担)、生活工学演習Ⅰ、II
大学院
生活工学特論、家庭科教育実践演習-生活工学とICT教育-、教科内容教材論-家庭科-(共坦)、健康・生活デザインセミナー(共担)
シラバスは、京都教育大学のシラバス検索ページから検索可能です。
卒業論文・修了論文など指導題目
卒業論文
2024年度
- 家庭科教育における生成AIの活用方法
2023年度
- 家電の使用方法に関する教材の提案
- ICTを活用した個別学習及び協働学習が眠気に及ぼす影響
- 学級経営に役立つオンライン学級づくりのツールと構成要素の検討
- 触覚の相違がコミュニケーションに及ぼす影響
- リアルタイム同調検出システムの評価
2022年度
- 動画教材制作を支援する動画編集技術パッケージの開発
- 学級経営における効果的な振り返り動画の構成要因
連絡先
〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町1番地
京都教育大学 教育学部 家政科 生活工学研究室